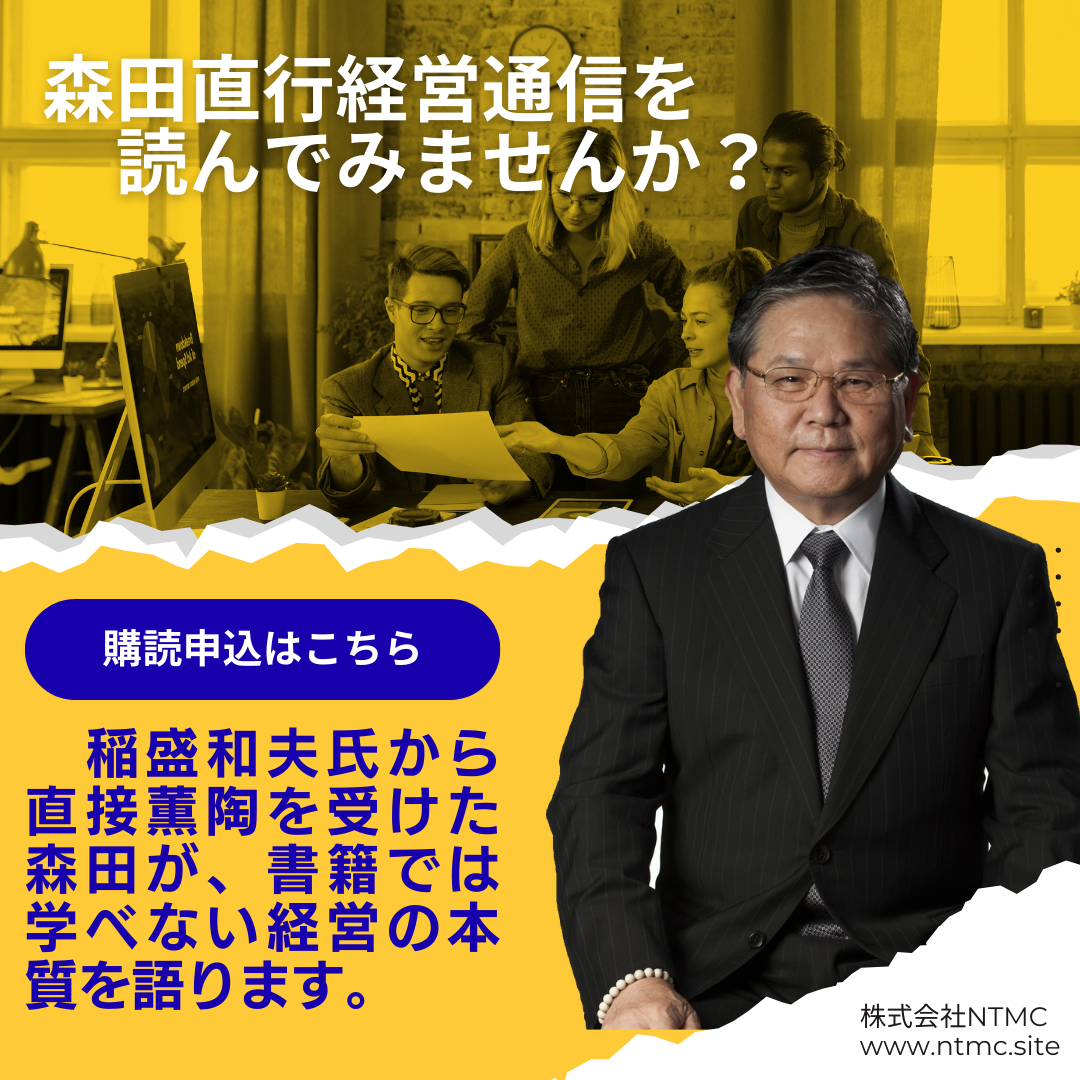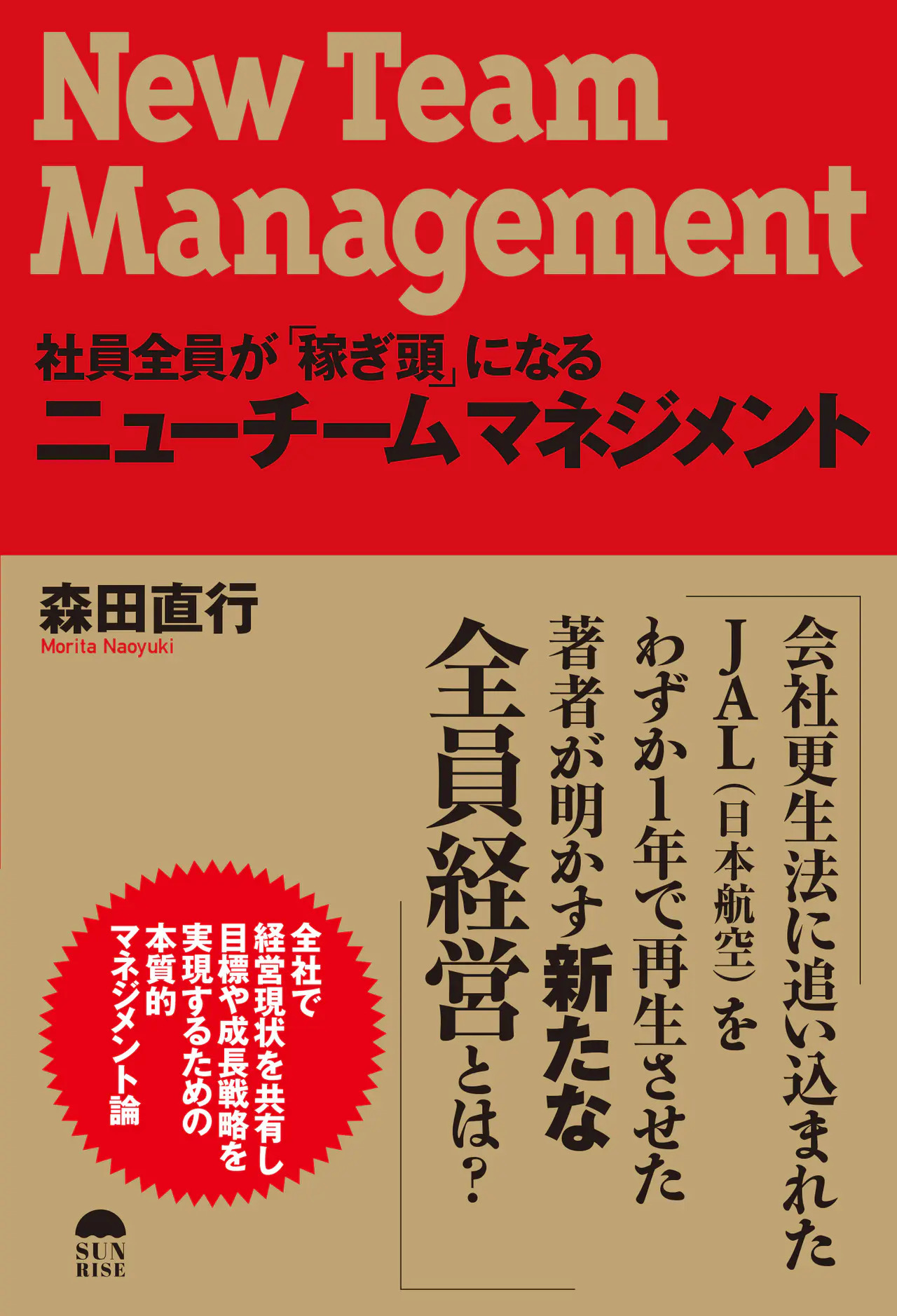社員の成長を後押しする!
新評価制度 勉強会・質問会を開催
株式会社NTMC 西日本コンサルティング部
松浦智和 tomokazu-matsuura@ntm-c.co.jp

企業名
株式会社スターシステム
住所
名古屋市中村区名駅5-28-1 名駅イーストビル5F
業種
各種ソフトウエアの企画・設計からシステムの開発・保守・運用業務
工作機械および搬送機等の機械設計・電気制御設計業務
ソフトウェア開発支援(技術者業務請負)
労働者派遣業務(派23-302457)
コンサルタントの松浦です。全員経営導入支援先である株式会社スターシステムにおいて、被評価者向け勉強会・質問会を開催しました。株式会社スターシステムは、社員一人ひとりの成長が企業の持続的な発展に不可欠であると考え、この度、従来の評価制度を抜本的に見直し、新たな評価制度構築に取り組まれました。先日実施した被評価者向けの勉強会・質問会の様子を交えながら、新制度導入の背景とその詳細、そして社員からの反響についてご報告いたします。
なぜ評価制度の見直しが必要だったのか〜「資格要件」導入の背景
新たな評価構築に着手した背景には、従来の評価制度が抱えていた特定の課題がありました。長らく運用されてきた評価制度は、社員の努力や成果をある程度反映していましたが、以下の二点が喫緊の課題として認識されるようになりました。
まず一つ目は、社員の自主性不足です。与えられた業務は着実に遂行するものの、自ら積極的に課題を発見し、改善提案を行うといった、より主体的な行動を促す仕組みが不足していました。これは、評価基準が不明確であったり、個人の成長と評価が直接的に結びつきにくいと感じられていたことが一因であると分析しました。
二つ目は、マネジメントの属人化です。各部門長に評価基準の解釈や運用が一任される傾向が強く、そのため部門間、あるいは部門長のマネジメント方針に差があり、結果的に評価の公平性にばらつきが生じる可能性がありました。これにより、社員が自身の評価に対する納得感を持ちにくくなるという問題も顕在化していました。
これらの課題を解決し、社員一人ひとりが自律的に成長し、企業全体の生産性向上に寄与できる組織を目指すために、「資格要件」による評価制度の導入を決定いたしました。この新制度は、単なる評価のためだけでなく、社員の能力開発とキャリア形成を強力に支援するツールとして機能することを目的としています。明確な基準を設けることで、社員は自身の目指すべき方向性を明確に認識し、自らの成長のために何に取り組むべきかを具体的に把握できるようになります。これにより、受動的な働き方から能動的な働き方への転換を促し、組織全体の活性化を図ることが可能となります。
「資格要件」とは?その仕組みと目指すもの
今回の「資格要件」に基づく評価制度は、社員が各等級において会社から求められる具体的な要件を明確に定義し、それに基づいて評価を行うものです。この要件は、以下の4つの主要な要件に分類されています。
- 理念要件
企業理念や社是、行動指針などを理解し、日々の業務において実践しているかを評価します。これは、社員が会社の目指す方向に共感し、その実現に向けて貢献する姿勢を育むことを目的としています。 - 人物要件
個人の成長意欲、チームメンバーとの協調性などを評価します。自己啓発への取り組みや、周囲との円滑な連携を通じて組織全体のパフォーマンス向上に貢献する姿勢を重視します。 - スキル要件
IT技術に関する専門知識やスキル、あるいはマネジメント能力を評価します。それぞれの等級で求められる専門性や役割に応じたスキルレベルの達成度を測ります。 - 業績要件
担当する業務における利益貢献度や、一人時付加化価値などを評価します。具体的な数値目標と連動させることで、社員の成果に対する意識を高めます。
これらの要件を明確にすることで、社員は自身の現時点での能力と、次の等級に進むために必要な能力とのギャップを具体的に把握することができます。これにより、自己成長のための具体的な目標設定が可能となり、自身のキャリアをより明確に描けるようになります。また、会社側も社員の能力開発に合わせた研修プログラムやOJTを計画的に実施することができ、個人の成長と会社の課題解決が密接に連携する仕組みとなっています。スターシステムでは、すでに各資格要件に沿った研修を開発しました。
この評価構築は、社員の自律的な成長を促し、組織全体のパフォーマンスを最大化することを目指しています。


評価制度への理解を深める 勉強会・質問会の様子
新評価制度の導入に際し、被評価者である全社員を対象とした勉強会・質問会を実施いたしました。実施の主たる目的は、新評価制度の仕組みを社員が深く理解し、それに基づいて高い評価を得られるようにすること、そして新しい評価制度が従来の評価制度よりも公正かつ透明性が高いことを明確に伝えることにありました。
勉強会では、新評価制度の導入背景から「資格要件」の具体的な内容に至るまで、詳細な説明、質疑応答を行いました。参加者は皆、真剣な表情で説明に耳を傾け、メモを取る姿が印象的でした。
特に、以前の評価制度に比べて会社に求められることが具体的な資格要件として明文化されたことで、質疑応答の時間には多くの質問が寄せられました。中でも、若いメンバーからは、資格要件の内容に関する具体的な質問が目立ちました。例えば、「〇〇のスキルは、どのレベルまで習得していれば良いですか?」「△△の要件は、具体的にどのような行動で示せば評価されますか?」といった、自身の成長に直結する内容への関心の高さが伺えました。彼らは、自身のキャリアアップを真剣に考え、新評価制度を最大限に活用しようとする意欲に満ちていました。
また、中途入社の社員からは、以前の会社での評価制度との比較に関する質問が多く寄せられました。「前職では、MBO(目標管理制度)を採用していましたが、資格要件との違いは何ですか?」「他社では、個人の成果だけでなくチーム貢献度も重視される傾向にありましたが、どのように考慮されますか?」といった質問が投げかけられ、当社の評価構築の独自性や、他社との違いを明確に理解しようとする姿勢が見られました。
印象的だったのは、「評価は絶対評価ですか、それとも相対評価ですか?」という具体的な質問が出た際のやり取りです。これに対し、担当者からは「一次評価は絶対評価ですが、最終的に同じ等級内での相対評価となります」と明確に回答しました。この説明は、社員が自身のパフォーマンスを絶対的な基準で高める努力をしつつも、最終的には組織全体の中でのバランスを考慮した評価が行われることを理解する上で非常に重要でした。このやり取りを通じて、参加者は新評価制度の公平性と透明性について、より深く納得することができたようです。
このように、活発な質疑応答を通じて、新評価制度に対する社員の理解を深めることができました。単なる制度の説明に留まらず、具体的な疑問や懸念を解消することで、社員の納得感を醸成し、新制度へのスムーズな移行を促すことができたと考えています。
参加者からの声〜社員の成長を真剣に考える会社の姿勢〜
今回の勉強会・質問会の実施後、参加者からは多くの肯定的なフィードバックが寄せられました。新評価制度に対する理解が深まったことに加え、会社が社員の成長を真剣に考えているというメッセージが伝わったことへの感謝の声が多く聞かれました。
ある参加者からは、「全員にこのような勉強会を開くことは非常に時間とコストがかかることだと思いますが、実施してくれたことに感謝しています。これで、自分が何をすれば評価されるのかが明確になりました。」という言葉をいただきました。また、別の参加者からは、「会社が自分たちの成長を真剣に考えてくれている、本当に社員を大切にしてくれている会社だと改めて感じました。新しい評価シートを元に、目標設定を頑張りたいと思います。」といった感動の声も寄せられました。
これらの声は、単に新しい評価制度が理解されたというだけでなく、会社と社員の間に強い信頼関係が築かれ、エンゲージメントが向上したことを示しています。社員が自身の成長を会社から支援されていると感じることは、モチベーションの向上に直結し、結果として生産性や創造性の向上に繋がると確信しています。今回の勉強会は、新評価制度の浸透だけでなく、社員のロイヤリティ向上にも大きく貢献したと感じました。
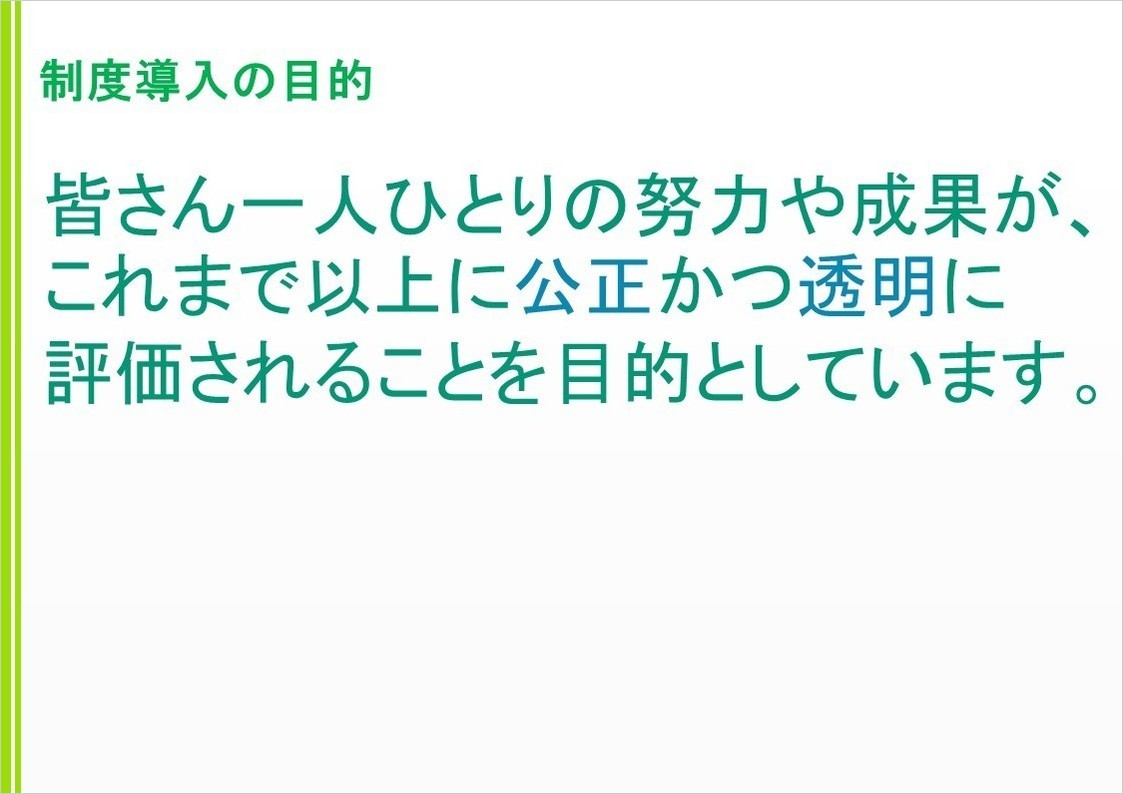
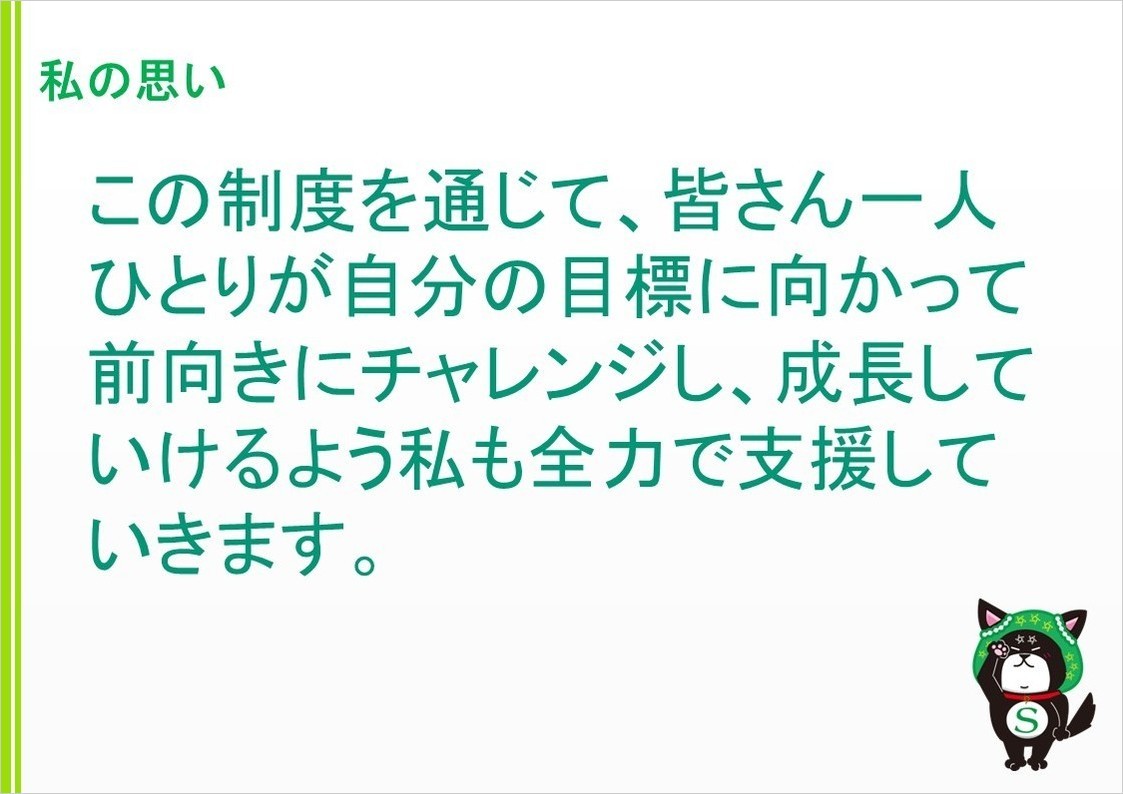
公正で透明性の高い評価制度で、さらなる企業成長へ
株式会社スターシステムは、今回の新評価制度の導入と、それに伴う社員向け勉強会・質問会の実施を通じて、社員の自律的な成長と企業全体の課題解決を目指します。
今回の評価構築は、従来の課題であった社員の自主性不足とマネジメントの属人化を解消し、社員一人ひとりが明確な目標を持って業務に取り組める環境を整備することを目的としています。理念要件、人物要件、スキル要件、業績要件という4つの柱に基づいた資格要件評価は、社員が自身の強みと課題を客観的に把握し、計画的な能力開発を促すための強力なツールとなります。
社員からの「会社が自分たちの成長を真剣に考えてくれている」という発言は、公正で透明性の高い評価制度が、単に個人の評価を行うだけでなく、会社と社員のエンゲージメントを深め、相互の信頼関係を強化することに繋がるというスターシステムグループの信念を裏付けるものです。
弊社は今後も、スターシステムグループが「資格要件」を基盤とし、定期的な見直しと改善を加えながら、社員が最大限のパフォーマンスを発揮し、自身のキャリアをデザインできる環境を構築できるよう支援していきます。社員一人ひとりの成長が、ひいては企業の持続的な成長へと繋がるという考えのもと、今後もより良い評価制度の運用支援に努めてまいります。
今回の記事が、評価制度の見直しをご検討されている経営者や人事担当者の皆様にとって、一助となれば幸いです。
❒ 購読のおすすめ
森田が稲盛和夫氏から学んだことや実務経験を通じ確立した経営哲学を企業経営、マネジメントに役立つメールマガジンとしてお送りします。
【購読無料】
❒ 全員経営を知る
サービス資料ダウンロードできます!
下記の語句は、株式会社NTMCの登録商標です。
「全員経営」「 社内協力対価」
「社内支援対価」「社内サービス対価」 「差引収益」「部門別連結管理会計」
「社内売買」「一人時収入」
「一人時経費」「一人時付加価値」
「全員で稼ぐ部門別採算」
「全員で稼ぐニューチームマネジメント」
「らくらく採算表」
「らくらく社内売買」 全14件
❒ 代表略歴・ごあいさつ
略歴
- 1967年 京都セラミック株式会社(現・京セラ株式会社)入社
- 1995年 同社代表取締役専務
京セラコミュニケーションシステム株式会社設立 代表取締役社長 - 2006年 京セラ株式会社代表取締役副会長
- 2010年 日本航空株式会社 副社長執行役員
- 2015年 株式会社NTMC代表取締役社長